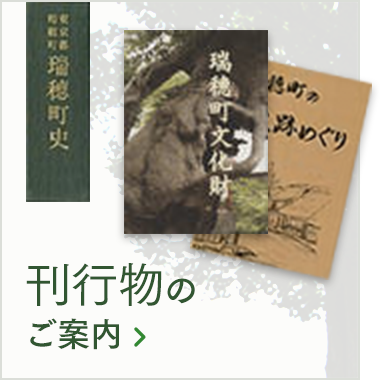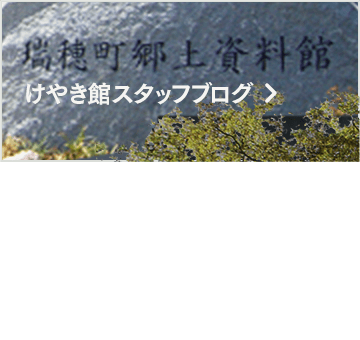みなさん こんにちは。
つるし飾りが始まって6日がたちました。
昨日、今日と暖かい春の日差しの中、連日たくさんの方が来館してくださり、嬉しいことですねぇ。
ありがとうございま~す。
そんな中、昨日は、かわいらしいお友達が見学に来てくださいました。
企画展示室に飾られているお花紙で作った雛人形は、狭山保育園の園児たちが作ってくれた作品なんですよ。
自分のお雛様を発見して「あったー!」「かわいい!」と歓喜の声があがりました。
そんな園児たちの作品は、会場を華やかに飾ってくれています。
ひなまつり展は、3月5日まで開催しています。
職員一同、みなさまのお越しをお待ちしておりま~す。
2019年02月18日
第97回 囲炉裏端で語る昔話
97回目を迎える囲炉裏端で語る昔話は、森田要助さんをお迎えして‘昔の思い出③’を語っていただきました。
機織りのパタンパタンという音をBGMに豚についての昔話を穏やかな語り口で思い出話が始まりました。
昔の家では、小さい豚を飼っていて家族の残りご飯を飼料としてあたえたり、糞をたい肥として使えるありがたい動物でした。
今では養豚業も少なくなり、豚を飼っているという家庭もなくなったので、昔のお話しが新鮮です。
次回の開催は3月10日です。お待ち申し上げます。
2019年02月16日
みずほ雛の春まつり2019 開催中!
みなさん、こんにちは!
毎年ご好評いただいている「みずほ雛の春まつり」、本日より開催しております! 🙂
正面玄関から入ると、大傘と七宝鞠、桃の展示がお出迎え! 😯


桃の展示の中には可愛らしいウグイスの姿が 😳
3羽いるので是非探してみてくださいね。
企画展示室では、段飾りや内裏雛など瑞穂町に伝わる雛人形を展示しています。

明治期の雛人形や、

狭山保育園の子供たちにつくってもらったおひなさまが飾ってあります。
(このおひなさまは企画展示室で作ることもできます!)

また、11時~12時、13時~14時に、けやき館ボランティアによるつるし飾り作りの実演も行っています。

アンケートに答えてくださった方には、実演でつくっている「にんじん」と「大根」の型紙をプレゼントしています! 😉
2階の展示ギャラリーでは、「懐かしの布たち」を開催しております!

たくさんの着物がずらりとなんでいます。
盛りだくさんの「みずほ雛の春まつり2019」は、3月5日(火)まで。

みなさまのご来場をお待ちしておりま~す!
こんにちは。
本日から、けやき館では‘みずほ雛の春まつり’が開催されています。
今日の折り紙教室はもちろん おひなさま!
小さい手で上手に折れました!
次回の折り紙教室は、3月16日です。
年度末のお忙しい時期ですが、皆様のご参加お待ちしております。
みなさんこんにちは。
今日は瑞穂第三小学校三年生の生徒さんを対象に、だるまについての授業を行ないました。
これは第三小学校の地域学習の一環で、地域の産業などについて調べ、ガイドブックをつくり、地域の宣伝大使になろうという学習です。
今回はだるまの歴史や作り方などを学習してもらいました。
だるまは張り子のため、木型をもとに、下張り紙、上張り紙を貼り、木型から抜いて、着色と乾燥を繰り返し、絵付けをして完成します。

むかしの道具とともに作り方を聞き、だるまの作り方を勉強する様子
瑞穂のだるまは養蚕との関わりで、明治時代頃から広まったといわれています。こうした歴史的な背景も学習してもらいました。
事前に学習してくれていることもあり、とても熱心に聞いてくれ、質問もたくさん出ました。

郷土資料館では、昔の生活体験を学習する社会科見学だけでなく、だるまなど地域のことを学習する手助けなどもしています。
第三小学校のみなさん、これからも地域のことに興味をもって学習してください。
2019年02月09日
第95回温故知新の会「寄木細工つくり」
こんにちは。今日は本当に寒い日ですね。
さて今回の温故知新の会は、体験教室「寄木細工つくり」が行なわれました。
この寄木は、昨年秋に当館で村山大島紬の絣板製造実演を行なった際の絣板を使用したものです。絣板を細く切り、つなぎ合わせることで一つの模様を作るという企画です。
まず、講師の坂田さんからの挨拶。
村山大島紬の絣板製造に長年携わっていたため、技術を皆さんの手許に残したいという思いをお話になりました。
早速、寄木細工の作成。絣板を細く削ったものをボンドで接着します。
 その後、乾燥させて周囲にヤスリをかけ、ニスを塗ります。
その後、乾燥させて周囲にヤスリをかけ、ニスを塗ります。
参加している方も幅広く、こだわりながら楽しく寄木を作っていました。
このイベントは、大人も子供も一緒になって楽しめるようでした。
今回は2日間の開催で、両日とも満員となりました。
次回の温故知新の会は、歴史講演会「面白い江戸の雑学」です。
皆様のご参加をお待ちしております!!
こんにちは 😀
今日は、雪も降ったりと本当に寒~い一日でしたね。
そんな中、けやき館では古今亭始さんの落語会を開催いたしました。

悪天候の中、多くのお客様にお越しいただきました。
ご来場の皆様、本当にありがとうございました。
演目は、「三方一両損」ほか。
皆さん 寒さも忘れ大笑い!!の一時をお過ごしいただきました。
次回の古今亭始さんの落語会は、6月に開催いたします。
どうぞお楽しみに!!
2019年02月03日
第94回 温故知新の会 打ち入れうどん
今日の温故知新の会は、郷土の食文化 ‘打ち入れうどん’。
講師に文化財保護審議会委員の川鍋悦子氏をお迎えし、賑やかに開催されました。
みんなで、わいわい言いながら作業開始!!
粉を混ぜ合わせ、練り、いい感じの硬さになったら、足で踏んで、伸して・・・
食べやすい太さに切ったら、野菜いっぱいのお鍋の中に・・
今回は、お醤油ベースの味に仕上げました。
みんな たくさん食べて、大満足!
次回の温故知新の会は、2月9日(土)、10日(日)に開催の「寄木細工つくり」です。
2019年02月02日
狭山丘陵市民大学2019「狭山丘陵のみちと石造物」講演会
みなさん、こんにちは。
2/2(土)、狭山丘陵市民大学2019「狭山丘陵のみちと石造物」講演会を行ないました。
狭山丘陵市民大学とは、狭山丘陵について理解を深めていただくため、東村山市・東大和市・武蔵村山市と瑞穂町が合同で行っている勉強会・見学会で、今年は「狭山丘陵のみちと石造物」というテーマで、全5回(講演会と見学会)で実施します。
今回はその初回として、青梅町方文書研究会会員の齋藤愼一さんに「石仏たちが見ていた街道の歴史」というテーマでご講演いただきました。
中世の鎌倉街道や日光街道、青梅街道を軸に、その街道の歴史や石造物について、エピソードを交えつつ紹介をしていただきました。
中世といえば、鎌倉街道と東村山市にある元弘三年板碑。造立した飽間齋藤氏と板碑造立の勧進についてお話がありました。
近世では、青梅街道を行き来する公用、私用の旅として、宿場の役割と石造物について注目されていました。近世になり、往来が増えることによる馬の増加と馬頭観音との関係、今とは違う夜の暗さと常夜灯の大切さなど、近世の人びとの生活の感覚が伝わってきました。また、聴衆の方々が興味を持っていたのは、蕎麦に関するお話でした。粉食文化が盛んだった多摩地域では、蕎麦が広く作られ、宿場などで食されていました。間食として好まれた蕎麦は、まさに江戸という一大消費地に近い狭山丘陵周辺ならではと語られていました。
4市町あわせて約70名という講演会でしたが、みなさんそれぞれに興味を持って聞いていました。
今後は各市町の見学会となり、第2回目は3月9日(土)、瑞穂町のみちと石造物を見学します。今回のイベントはすでに予約が終了していますが、来年度以降も継続しますので、興味のある方はぜひお申し込みください。
お待ちしています。

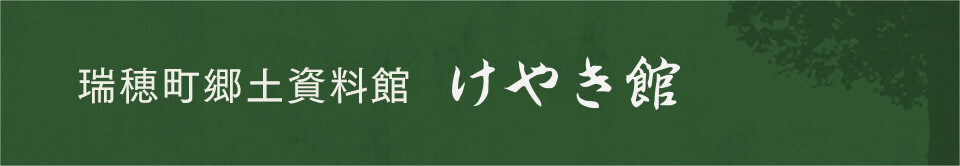

















 その後、乾燥させて周囲にヤスリをかけ、ニスを塗ります。
その後、乾燥させて周囲にヤスリをかけ、ニスを塗ります。