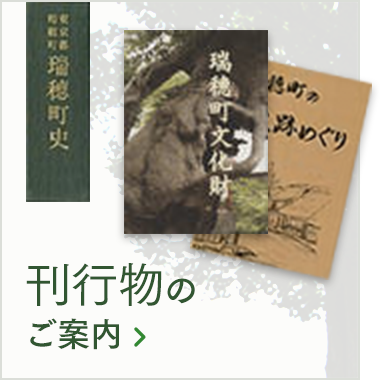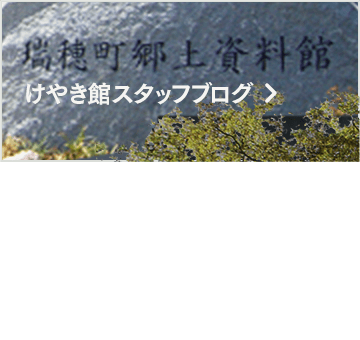こんにちは。
本日けやき館では秋晴れの中「インド藍 板締め染色教室」を開催しました。
みなさんは“板締め染色”をご存知ですか?
板締め染色は、かつて瑞穂町で盛んに生産されていた村山大島紬の糸を染める染色技法です。
今回は、日本の伝統工芸士 小山典男氏を講師にお招きし、この染色技法を使ってストールをインド藍で染めました。
まず、絣板の上にストールを置いていきます。ストールの置き方によって縞柄の出方が変わってくるので、参加された方は真剣にストールの置く位置を決めていました。

ストールを乗せ終わったらボルトできつく締め、インド藍の液がたっぷり入ったプールに入れて染色しました。
染色後は芝生の上で乾燥させ、作品発表会をおこないました。

ステキなストールが沢山できあがりました。
11月1日から始まる「みずほ染め織り作品展」では、講師の小山先生の板締め染色作品がご覧いただけます。
ぜひ、ご来館ください。おまちしております。
2019年10月25日
Trick Or Treat !!
ハッピー ハロウィン!
みなさま こんにちは

ただ今けやき館では、オバケかぼちゃ達が、皆様をお出迎えしております。。
「ゆめちゃんのハロウィン」「ハロウインドキドキおばけの日」「ハロウィンのおばけ屋敷」
絵本もご用意しました。
是非、遊びにきてください。
2019年10月21日
第111回温故知新の会「絣板職人の語る村山大島紬と絣板のしくみ」
みなさん こんにちは。
先日、第111回温故知新の会 地域の産業に関する講演会「絣板職人の語る村山大島紬と絣板のしくみ」が開催されました。
講師は元絣板職人の坂田勝長さんです。

講師の坂田さん
村山大島紬といえば、瑞穂町の伝統産業として知られていますが、着物文化が遠のいた現在では生産はできなくなっています。
今回はそんな村山大島紬の「絣板のしくみ」にこだわった講演会です。
絣板は村山大島の特徴である“精緻な柄”と“生産の効率”を両立させる、大切な役割を果たしました。絣板を彫るための板図案には、多くの工夫がこらされています。
一つ紹介すると、経糸の絣板には柄の「ミミ」と呼ばれる部分があります。柄と柄との間の部分で、絣板職人の方はこの「ミミ」の部分を一枚一枚ずらしながら縦板を彫っていました。もし「ミミ」の部分を柄の同じ高さの位置に設けていますと、同じ箇所に染まらない筋が生まれてしまうためです。
坂田さんからは柄をどのように絣板に移していくか、道具の説明など、細かく丁寧に説明してくださいました。
続いて、もう一人の講師、文化財保護審議会の平山会長が絣板で染めた糸がどのように織物になっていくか説明してくださいました。平山会長は元機屋さんで、経験を交えながら絣板で染められた糸が織り上げていくまでを映像や実演を交えながら説明をされていました。

解説をする平山さん
来場された方は、坂田さんの出身である石畑地区の方が多かったため、和やかな雰囲気で講演会が進みました。映像を見ながら、「この光景は昔見たな」とおっしゃる方も。
最後には織物組合が作曲し、よく歌われた村山音頭を合唱して締めくくりました。
次回の温故知新の会は、10月27日(日)の第110回 温故知新の会「東京狭山茶手もみ実演」(第2回目)です。13日に続き、貴重な狭山茶の手もみ実演を見ることができます。予約にはまだ若干余裕があります。ぜひご参加ください。
2019年10月20日
第113回囲炉裏端で語る昔話
皆さん、こんにちは。
今日は囲炉裏端で語る昔話が行われました。
お題は『水道の始まり』、語り部はくっちゃべり会の関谷さんと中村さんです。
人の生活にかかせない水道。
どのように作られてきたか、歴史的要素を盛り込みながらお話しされました。


次回は11月3日(日)です。
皆さんの来館をお待ちしております。
2019年10月19日
瑞穂ふるさと大学2019 歴史コース
みなさん、こんにちは。
前日からの雨が心配されましたが、本日10月19日(土)、瑞穂町教育委員会 教育部 図書館文化財担当主催による
「瑞穂ふるさと大学2019 歴史コース」が無事実施され、私も参加者のみなさんと一緒に2時間ほど町歩きをしてきました。

ふるさと大学は、自然・観光・歴史の三つのコースがあり、各コースとも地域めぐり・講座・検定からなっています。本日の地域めぐりは、けやき館嘱託員の滝澤福一先生を講師として、コース案内と各ポイントでの丁寧で分かりやすい解説をしていただきました。

また今回は、一般の方々とともに、瑞穂農芸高校の先生と食品研究部の生徒のみなさんも参加してくれました。

普段生活している町の中にも、まだまだ知らないことがたくさんあり、参加者は滝澤先生の説明に熱心に耳を傾けながら、うなずいたり質問をしたりして、町の魅力を再発見するとともに、有意義なひと時を過ごすことができました。
なお、歴史コースの講座と検定は、12月7日(土)に行われます。

皆さん、こんにちは。
雨も上がり、すっかり秋めいてきましたね。
急に寒くなり、体調を崩して、風邪を引いている方もいます。
気をつけてお過ごしくださいね。
今日は折り紙教室が行われました。
お題は「ほしぐるま」です。


いくつか小さな物を作り、組み合わせます。
こちらでは、3名の講師の方々が手取り足取り、丁寧に教えてくださいます。
初めての方でも安心です!
次回は、11月16日(土)です。
皆さんの参加をお待ちしております。
本日は劇団スタジオライフの皆様による影絵劇の上演を開催しました。
上演作品は『てぶくろを買いに』 『100万回生きたねこ』。
『100万回生きたねこ』。

どちらも名作ですね。
途中ワークショップでは、手影絵をクイズ形式で楽しんでいただいたり、 実際にお子さんが参加して即興影絵を上演したり
実際にお子さんが参加して即興影絵を上演したり

会場は笑いの渦に包まれました。(実際に小学生の参加者が影絵を動かしている写真)
連休の最終日。沢山のご家族連れが鑑賞してくださり、劇団員の方も喜んでいらっしゃいました。
これからもご家族で楽しめるイベントを企画しますので、是非ご来館ください。
2019年10月13日
第110回 温故知新の会「東京狭山茶手もみ実演」
みなさん、こんにちは。
台風一過で秋晴れの10月13日(日)、けやき館では、第110回 温故知新の会「東京狭山茶手もみ実演」を行いました。
東京狭山茶の製法は、江戸時代の1800年頃に地元の先人たちが考案したとされています。
今回は、全国手もみ製茶技術大会で入賞した実績をもつ「東京狭山茶手もみ保存会」から講師の方々をお迎えしました。

講師の方に説明をしていただきながら、参加者も実際に手もみを体験しました。

また実演の後は、手もみの茶葉でいれたお茶をいただきましたが、参加者一同、そのまろやかな味とうま味に、驚きの表情でした。
まさに、狭山茶の味にとどめをさされたということでしょうか。

10月27日(日)にも今日と同様の内容で実演会を実施しますので、
今回ご都合がつかなかった方は、是非とも奮ってご参加ください。
こんにちは。
一昨日、11日は十三夜でした。
芋名月の十五。栗名月の十三夜。
どちらか一方だけのお月見は“片見月”と呼ばれ縁起が良くないと言われています。

十一日に十三夜を忘れてしまった方は、
けやき館に十三夜飾りを楽しみにいらしてください。
15日まで楽しめます。
2019年10月13日
第112回囲炉裏端で語る昔話
みなさま こんにちは
台風19号が過ぎ、良い天気になりました。
みなさま、無事に過ごされたことと願っております。

さて、この行灯、美しい布がはられています。
こちらの生地が“村山大島紬”です。
本日の囲炉裏端で語る昔話は高橋公江さんをお迎えし、
「瑞穂のはたおり」についてお話ししていただきました。
瑞穂の機織りといえば、“村山大島紬”
この“大島”とは、奄美大島のことです。何故奄美?と私も思っておりましたが、
この行灯のように美しい模様、これが奄美の紬の模様に似ていることから大島をつけて
村山大島紬といわれるようになったそうです。
ですから村山大島紬に対して、奄美の紬を“本場紬”といったりもするそうです。

農家の副業として行われていた機織りがいかに当時の瑞穂の人々の生活を支えていたか、
また“日本のシルクロード”(八高線から横浜線)にまでおよぶ養蚕の話などが、
高橋さんの優しい語り口で語られ、心地よい囲炉裏端となりました。
「みずほの機織り」は、第2回も行われる予定です。(日程は未定)
皆さまお楽しみに。
次回の 囲炉裏端で語る昔話は、
10月20 日 『水道の始まり』語り部:くっちゃべり会 関谷氏、中村氏のお二人です。
皆さまのお越しをお待ちしております。


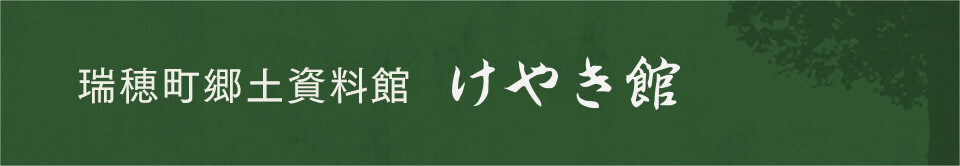












 『100万回生きたねこ』。
『100万回生きたねこ』。
 実際にお子さんが参加して即興影絵を上演したり
実際にお子さんが参加して即興影絵を上演したり