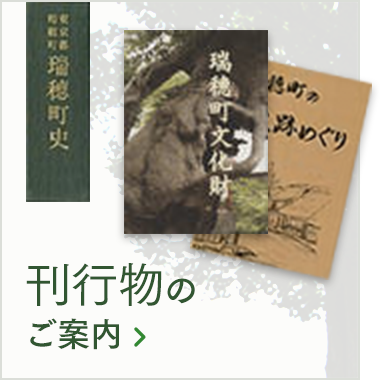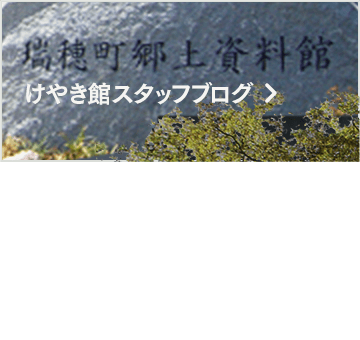2024年10月13日
手もみ実演がケーブルTVで放送されます
みなさん、 こんにちは。
今日、けやき館では先週に続いて「東京狭山茶手もみ実演」が行われました。
実は今日の手もみ実演では、地元の瑞穂ケーブルテレビの番組収録がありました。

今年度から瑞穂ケーブルテレビでは、けやき館を紹介する「なるほど!・ザ・みずほ」という番組を放送しています。
11月は東京狭山茶を放送する予定です(番組内容は毎月変わります)。
手もみ製法の実演をご覧になりながら、東京狭山茶の魅力をたくさんの方々に知っていただければと思います。
実演してくだっさった「東京狭山茶手もみ保存会」のみなさん、ありがとうございました。

瑞穂ケーブルテレビの「なるほど!・ザ・みずほ」は、
毎日6時45分から7時、13時から13時15分
の二回放送しています(内容は同じです)。
瑞穂ケーブルテレビをご覧になれる環境の方は、ぜひ見てくださいね。
2024年09月21日
「古民家で楽しむ紙芝居」を開催しました
みなさん、こんにちは。
暑かった夏も、ようやく終わりに近づいてきた感じですね。
本日けやき館では、第21回「古民家で楽しむ紙芝居」を開催しました。
1作目は「殿ヶ谷の将門ばなし」です。
昔むかし、平将門の一行が青梅に向かっている途中、戦に疲れたため病にかかってしまいました。近くの神社に助けを求めると、神主から秘伝の薬を飲ませてもらい、たちまち元気になりました。その薬には、「キササゲの実」(=梓実)が調合されていたことから、後にこの神社は阿豆佐味天神社(あずさみてんじんじゃ)と呼ばれたそうな。瑞穂町にも平将門にまつわる伝承があったのですね。

2作目は、町の図書館からお借りした「ふくろうのそめものや」です。
染物屋を始めたフクロウのもとに、注文の多いカラスがやってきました。自分の体をもっときれいに染めろと、フクロウに無理な注文をしたところ……。
カラスの体の色が黒くなった理由が、なるほど!と分かりました。

「古民家で楽しむ紙芝居」全10作品は、YouTubeでご覧いただけます。
他の9作品もぜひご覧になってください。
次回の「古民家で楽しむ紙芝居」は11月23日(祝)の開催で、曽我兄弟の仇討ちにまつわる「五郎松・十郎杉」を上演する予定です。
みなさんのお越しをお待ちしております。
みなさん、こんにちは。
絵本作家の伊藤知紗さんから、新しい絵本をご恵送いただきました。
伊藤さんは昨年の夏期の展示「伊藤知紗 絵本原画展~昆虫観察日記~」などでお世話になっています。
昆虫をテーマにした絵本を数多く発表されていて、フィールドでの自然観察に基づいた自然や昆虫の描写が特徴です。
1冊目は、『だんごむしとまんまるおつきさま』(ひかりのくに株式会社、2024)です。こちらは「おはなしひかりのくに」シリーズとして2017年に刊行、今回ハードカバー化された本です。

〈『だんごむしとまんまるおつきさま』表紙〉
植木鉢の下に住むダンゴムシ、‘ぽろんた’ ‘ごろんた’ ‘ぷちんた’ ‘たまよ’ ‘くるりんた’ たちは、十五夜につきみだんごを作って、お月見を楽しみに待っていますが…、というお話です。
ダンゴムシの好む、植木鉢の下を伊藤さんがどのように描いているか注目してみてください。
2冊目は『がくしゅうひかりのくに』7月号(ひかりのくに株式会社、2024年7月)より、「せみをさがしに」です。

〈『がくしゅうひかりのくに』表紙〉
夏の絵本ということで、セミの羽化する場面が描かれているのですが、少しずつ背中が盛り上がり、足を抜いていく様子がとてもわかりやすく表現されています。
どちらもデフォルメを効かせている描写ですが、とてもよく観察して描いていることがわかります。
けやき館の図書コーナーに配架しますので、ぜひ手に取ってみてください。
伊藤さんありがとうございました。
2024年09月12日
写真から見る瑞穂2中職場体験
みなさん、こんにちは。
今週は瑞穂第二中学校の職場体験生2名を受け入れていました。
今回は記録の写真から抜粋して、職場体験の様子をお伝えします。

〈瑞穂町の歴史講義中〉
この写真は瑞穂町の歴史についての一コマです。
文化財などを通して瑞穂町の歴史について講義を聴いているところですが、生徒の前にあるカードは、各時代のカード、文化財のカードです。
中学校では歴史の勉強をしている最中で、正確に各時代を並べ替えるのは難しいと思います。さらに、どの時代にどのような文化財があったのか、カードを使って勉強をしているところです。

〈写真撮影の様子〉
続いては写真の撮影をしているようですが…。
これは古文書の撮影をしているところです。三脚を使って、古文書と水平に、写真を撮るのは意外と難しいことです。
そこで、水平器を使ってカメラが水平になっているか確認しながらセットしています。見やすい写真を撮るというのも準備が肝心です。
更に整理番号や裏の文字を気にするなど、注意は多岐にわたります。なお、3日間の実習で一番大変な時間だったと後で聞きました。

〈何やら根を詰めて話し合っている様子〉
この写真は企画会議の一コマ。
イベントを企画する際、いつ実施するのか、講師はどうする、時間はどのように設定するのか、多くの課題に直面します。
実施日が決まると、広報はいつから開始するのか、実施場所が決まると定員は何人が適当なのかなど…。
えっ、こんなことまで考えるの?と生徒さんは思ったのではないでしょうか。
でも、一つ一つ考えないと、よりよいイベントは作ることができないとも感じてくれたのではないでしょうか。
3日間、おつかれさまでした。
みなさん、こんにちは。
けやき館では、9月3日(火)から5日(木)まで3日間、瑞穂中学校の職場体験実習として、2年生3人を受け入れていました。
3日間で中学生はどのような活動をしてくれていたのか、ご紹介します。
〇1日目
1日目はガイダンスと瑞穂町の歴史を学んでもらいました。
展示や施設など館内を案内したり、けやき館は年間どのような活動をしているのか、どのような方の協力を得て活動しているのか説明したりして、けやき館について知ってもらいます。
ちなみに、生徒たちは何度かけやき館には来てくれていて、地域の勉強をするために活用してくれた生徒もいると聞きました。
続いて、瑞穂町の歴史について。
地域の歴史について、小学校の地域学習の時間で習いますが、改めて勉強する機会は意外とありません。
そこで、町の文化財などを紹介しつつ、中学校で習う歴史と地域の歴史を重ね合わせて学んでもらいます。
 〈瑞穂町の歴史の学習〉
〈瑞穂町の歴史の学習〉
〇2日目
2日目はクイズ作成と自然についてです。
クイズ作成は、常設展示室のめくりクイズの作成を一人一問作成してもらいます。テーマを探し、一人で問題、解説を作る。
小さい子にも、大人にも分かるようにクイズを作成するということは、意外に難しいことですが、それぞれテーマを見つけ、調べながら作成してくれています。
風除室に展示されているカブトムシコーナーのお手伝い。
カブトムシが集まるシマトネリコの植え替え、土に産みつけられたカブトムシの卵や幼虫の割り出し作業をしました。
それによりカブトムシの成虫に加え、卵から3齢幼虫の各ステージを観察することができました。
 〈自然、割り出し作業中〉
〈自然、割り出し作業中〉
〇3日目
最終日は史跡見学と体験教室の企画です。
街中を歩くと、路傍の石塔を目にすることはありませんか。
普段はそのまま通り過ぎてしまいがちですが、よく見ると、それは歴史の証人になってくれるかもしれません。
この史跡見学でも、けやき館から歩いて行ける範囲の身近な石塔や文化財を解説付きで見ています。
けやき館では、体験教室にも力を入れています。工作教室や染色、機織りなどの体験教室は、教育普及活動の一環。
企画を立てるためには、講師を探して交渉、チラシを作ったり、当日までの準備をしたりしないといけません。
一つ一つの企画にも、いろいろな準備が必要であるということを知ってもらえたと思います。
 〈体験教室の企画会議の様子〉
〈体験教室の企画会議の様子〉
そして、最後にめくりクイズ完成の発表会です。



〈めくりクイズの発表会〉
以上、3日間の主な実習内容でした。
地域の歴史や自然について学びながら、郷土資料館の仕事に触れることで、働くことについて感じ取ってもらえたら幸いです。
瑞穂中学校の実習生のみなさん、お疲れさまでした。
2024年08月25日
温故知新の会「江戸時代の警察組織と罰」を開催しました
みなさん、こんにちは。
毎日残暑が続き、暑さは一向に収まる気配がありませんね💦
けやき館では今日、第226回温故知新の会「江戸時代の警察組織と罰」を開催しました。講師は、瑞穂町文化財保護審議会委員で瑞穂古文書を読む会の代表の務める塩島清志さんです。

江戸時代の警察組織としては、江戸において町奉行・勘定奉行・寺社奉行があり、その特徴としては縦割り組織で弊害が多かったこと。瑞穂町の旧村々では、箱根ヶ崎村や殿ヶ谷村などは幕府領(いわゆる天領)、富士山村や二本木村などの旧元狭山村は旗本領で支配者が異なっていたことや、関東取締出役や寄場組合といった治安維持組織の説明がありました。
また、江戸時代の刑罰の種類や現代との違いなど、具体的な例を交えて詳しく話してくださいました。時代劇などを見て、分かっているようで実はよく知らなかった江戸時代の実像について、理解を深めることができた講演会になりました。
これから、けやき館で開催する温故知新の会は、以下の通りです。
・9月1日(日) 体験教室「東京だるまの絵つけ体験」 ※定員に達しました
・9月21日(土) 自然に関する講演会「定点カメラが見た野鳥たち」 受付中
・10月6日(日)・13日(日) 地域の産業「東京狭山茶手もみ実演」 9月5日(木)より受付開始
・10月20日(日) 歴史講演会「消え去った言葉たち」 9月20日(金)より受付開始
みなさんのお越しをお待ちしております。
2024年07月22日
特別展関連企画「おもしろ動物を作ろう!」
7月21日(日)に「おもしろ動物を作ろう!」を行いました。
このワークショップは、現在開催中の「江幡三香 木のえほんWOOK展」の関連企画です。
6月30日にはおとな向けの「木のえほん作り」を行いましたが、今回は子ども向けです。

講師は彫刻家でありおもちゃ作家である江幡三香さんです。
江幡さんが作品づくりをするときに出る、使われない部分-木っ端-を使っておもしろい動物を作ってみよう!というワークショップです。

はじめに、使いたい木っ端を選びます。木の実やかんなくずなどもあります。
おもしろい形がたくさん!選ぶのもワクワクします。

どんなふうにしようかなぁ~。

やすりがけをして、木工用ボンドやホットボンドでくっつけていきます。

裏ワザ!竹串を使ってつなげるようにドリルで穴をあけてもらう子も!

時間が経つにつれ、どんどん集中力が増して熱中していく姿も見られました。

最後は、みんなの作品をならべて発表会です。

その名の通り“おもしろ動物”がたくさん出来上がりました‼
すべてをご紹介したいところですが…泣く泣く一部をご紹介。


↑ ワニさん。りんごを口の上に乗せています。
ご参加いただいた皆さま、江幡さん、ありがとうございました。
2024年06月20日
けやき館の七夕かざり&瑞穂俳句会の俳句展示
みなさん、こんにちは。
今日も暑いですが、ようやく梅雨入りが目前になってきましたね。
けやき館では、今年も風除室で「けやき館の七夕かざり」と「瑞穂俳句会の俳句展示」を行っています。

七夕かざりでは、石畑保育園・東松原保育園・みずほひじり保育園の園児のみなさんが、願い事を書いてくれた短冊176枚を飾りました。



俳句展示では、瑞穂俳句会の16人の方々が「星まつり五七五 ~大けやきと耕心館を詠む~」のお題で、二句ずつの俳句を短冊にしたためました。
風除室のドアが開くたびに、風に揺られて涼しさを運んでくれます。

七夕かざりと俳句作品は、7月7日(日)まで展示しています。けやき館にいらした際は、是非足を止めてご覧になってください。
みなさんのお越しをお待ちしております。
みなさんこんにちは。
本日は板碑の拓本体験を実施しました。
板碑は中世の供養塔の一つです。今回は瑞穂町周辺の板碑の拓本をとることで、どのようなことが刻まれているのか読み取ろうという講座です。
 〈拓本体験の様子〉
〈拓本体験の様子〉
まずは、板碑や拓本をとる意味についてお話します。
今までに拓本をとったことがある方、今日初めて板碑に触れる方、どちらもいらっしゃいました。
拓本をとることで、凹凸がはっきりわからなくなってしまった銘文でも読めることがあります。
また、記録することでその時点での板碑の状態を記録することができます。
次に板碑の拓本をとる手順です。
霧吹きで水分を与えつつ、板碑と紙とを上手く密着させていきます。
 〈画仙紙の空気を抜いています〉
〈画仙紙の空気を抜いています〉
板碑全体の空気を抜き、ほどよくタオルなどで湿気をとったら、タンポで板碑全体をムラなく墨を打っていき、完成となります。
 〈真剣に拓本をとっています〉
〈真剣に拓本をとっています〉
みなさんの拓本がとれたら、埼玉県にある板碑を例にお話をしました。
身近なところにも板碑があったことを知るきっかけになったのではないでしょうか。
 〈映像にて埼玉県の板碑の紹介〉
〈映像にて埼玉県の板碑の紹介〉
2024年05月19日
地域めぐり「二本木から箱根ケ崎の歴史散歩」に行ってきました
皆さん、こんにちは。
五月も半ばを過ぎ、暑い日が続くようになりましたね。
昨日、けやき館では第220回温故知新の会「二本木から箱根ケ崎の歴史散歩」を開催しました。講師は毎年お世話になっている角田清美さんです。
角田さんの歴史散歩は、けやき館でも人気の講座です。今年は都県境にある入間市の壽昌寺からスタートしました。壽昌寺は臨済宗建長寺派のお寺で、角田さんによると多摩地方には臨済宗のお寺が多いとのことでした。

途中の道すがら、さまざまな説明があり、地形・地名はもとより歴史やその由来、樹の高さの測り方、話が脱線してお茶の説明から世界史まで、次から次へと私たちを話で魅了してくださいました。もちろん参加された方々も大満足でした。

日差しが強く暑い日にもかかわらず、参加者の皆さんお疲れさまでした。そして角田さんありがとうございました。来年もまた楽しみにしています。


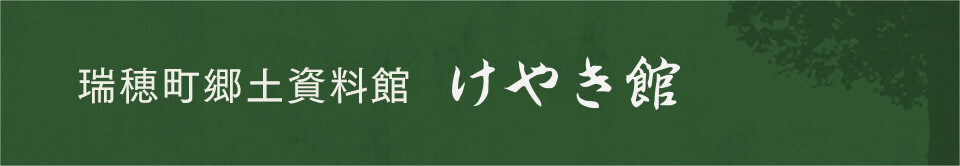








 〈瑞穂町の歴史の学習〉
〈瑞穂町の歴史の学習〉 〈自然、割り出し作業中〉
〈自然、割り出し作業中〉 〈体験教室の企画会議の様子〉
〈体験教室の企画会議の様子〉


















 〈拓本体験の様子〉
〈拓本体験の様子〉 〈画仙紙の空気を抜いています〉
〈画仙紙の空気を抜いています〉 〈真剣に拓本をとっています〉
〈真剣に拓本をとっています〉 〈映像にて埼玉県の板碑の紹介〉
〈映像にて埼玉県の板碑の紹介〉